ad
プライバシーポリシー
2025.06.21
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2020.05.17
跳び箱
小学生になって最初に体育館で跳び箱を見たとき、なぜかそれに違和感がなかった。
それまで見ていたわけでも知っていたわけでもないのに、なぜか不思議なものに思わなかったことをはっきりと思い出す。
それがきっと「学校」というものなんだろうと、勝手に納得したことなのだろう。
跳び箱は、やってみると、案外と上手に飛べたものだった。
馬跳びとかやるようになったのはその後のこと。
普通に飛べたことが面白くなった連中が体育の時間でないのにやりたがった。
跳び箱の飛び方、それをクチで教えられたら普通にできたのだ。
ところが、どうしてもなかなかこの跳び箱がうまくできない子というのがいて、いつもなぜかまごまごと固まって遠慮がちに引っ込んでいた。
それはきっと、何か別の価値感があって、跳ぶのを邪魔しているような気がしたものだ。
言葉では理解できない、どうしても受け付けない何かの価値観ゆえに跳べない。
そんなある種の障壁を感じたものだ。
そのことが気になったものだから、自分が何段飛べるようになるかなんてあまり興味は起きず、むしろいつまでも少しも飛べない子のことを考えていた。
今も思う。
あれはいったいなんだったんだろうか、と。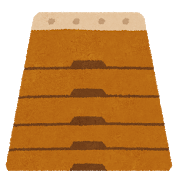
ひょっとしたら、あの時、跳べなかった子たちというのは、実は異星人で、そして妙に跳び箱を怖がっていたとか?
一時的に異性人が乗り移っていて、それで跳べなかったとか。
それは冗談としても、それほどの断絶を感じたのは事実だ。
PR







